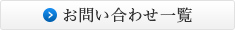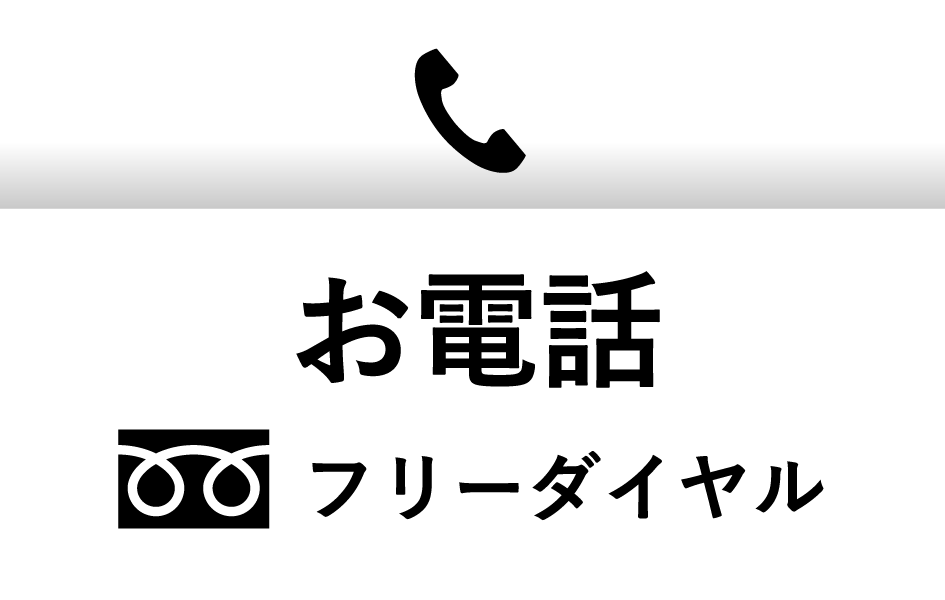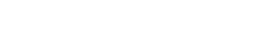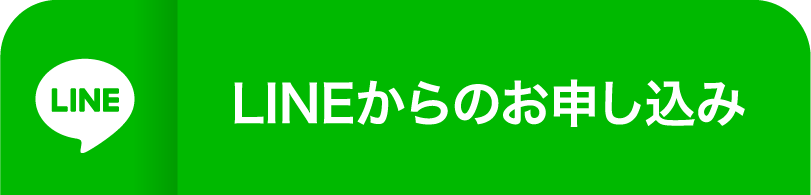監修者紹介
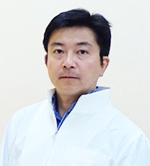
- 稲葉 岳也
- いなばクリニック
日本耳鼻咽喉科学会認定 耳鼻咽喉科専門医 日本アレルギー学会認定 アレルギー専門医
東京慈恵会医科大学卒業後、千葉大学大学院にて医学博士取得。東京慈恵会医科大学附属病院、聖路加国際病院を経て、2004年にいなばクリニックを開業。
皮膚科・形成外科領域のレーザー治療、及びアレルギー疾患の総合的治療が専門です。皮膚科、美容皮膚科、形成外科、美容外科、耳鼻咽喉科、呼吸器内科、アレルギー科を主体として、幅広い視点で総合的な診療を行っております。レーザー機器を導入した医療を行っており、幅広い年齢層を対象としたホームドクターとして、地域密着の診療に尽力しております。
以前より抜け毛が増えた、髪にボリュームがなくなった、同年代に比べて髪が薄い気がする、そんなことを不安に思った経験はありませんか?
ストレスや不規則な生活、食生活の乱れなど、忙しい私たち現代人を取り巻く環境は髪にとってあまり良い環境とはいえません。
この記事では、抜け毛の原因から対処法まで徹底的に解説しています。
あなたも今日から抜け毛対策を始めましょう。
目次
予防の前に抜け毛の原因を探る!

男性ホルモン
(出典:(1)男性型脱毛–その特性と未来像 Androgenic alopecia–Its characteristics and perspectives)
抜け毛が増える原因の1つは男性ホルモン (テストステロン)です。しかしテストステロンは直接脱毛に関係しているわけではありません。
テストステロンは体内で5αリダクターゼという酵素によりジヒドロテストステロン(DHT)に変換されます。このDHTが毛根にある受容体に結合し脱毛の指令を出すことで、髪が抜け落ち、男性型脱毛症(AGA)が発症するのです。
この酵素の量には生まれつき個人差があり、酵素の活性度合いによってAGAの発症するか否かが決まります。
生活習慣
(出典:(2)髪の健康を考える〜美しい髪で過ごすには〜)
抜け毛と生活習慣には深い関わりがあり、抜け毛を治療するうえで切り離すことはできません。
夜更かしや昼夜逆転などの生活リズムの乱れ、油ものや炭水化物メインの乱れた食生活、喫煙、睡眠不足、過度のストレスなどは、自律神経やホルモンバランスの乱れを引き起こし、抜け毛を促進させる原因となります。
抜け毛を予防するには、まず生活習慣の改善を行うことが大切です。短期間で一気に抜け毛を予防することは難しいため、毎日小さなことから継続を心がけましょう。
遺伝
(出典:(3)薄毛・脱毛の原因遺伝子の発見 キューティクル層を構成する Sox21 タンパク質の機能)
確かに抜け毛と遺伝は密接に関係があります。もし親族に薄毛の人がいる方は、自分と重ねて不安になるかもしれません。
しかし抜け毛の遺伝子が引き継がれたとしても、必ず抜け毛や薄毛が進行するわけではありません。遺伝子の発現に加え、その人の髪質、生活環境などの複合的な要素により、抜け毛が起きやすいかどうかが決まります。
薄毛の体質が遺伝しても発現しない可能性があることを覚えておきましょう。
年齢
(出典:(4)毛髪の科学と診断 第4版)
健康な髪の発毛サイクルは3段階を経て抜け落ちていきます。まずは髪が発育する4~6年の成長期、毛母細胞の成長が止まる2~3週間の退行期、髪が抜け落ちる数か月の休止期です。
年齢が上がるにつれ、発毛サイクルが乱れ、休止期が長くなる傾向にあります。休止期が長くなることで、新しい髪が生えるまでの期間が遅い、抜け毛が多い、髪が細い、ボリュームが減り、抜け毛や薄毛を意識しやすくなります。
ストレス
(出典:(5)髪の健康を考える〜美しい髪で過ごすには〜)
日常生活における過度なストレスは、抜け毛を増やす原因になります。ストレスがあると体内の自律神経やホルモンバランスの乱れを引き起こし、髪は正常な発毛サイクルを保てません。
ストレスは交感神経を刺激して頭皮の筋肉を硬く緊張させる一因です。固い土には良い作物が育たないように、硬くなった頭皮は血流が悪く髪に十分な栄養が行き渡らないため脱毛しやすくなります。
加えてストレスがたまると暴飲暴食をしたり生活習慣が乱れがちになるため、普段から適度にストレスを発散するよう心がけましょう。
紫外線
(出典:(6)毛髪の紫外線ダメージ—評価指標とダメージケア—)
抜け毛を予防するには紫外線対策も併せて行いましょう。紫外線は髪の毛や頭皮にダメージを与え、細胞の中の遺伝子を傷つけることがあります。すると正常な毛髪サイクルを保てずに、健康な髪の毛を発毛させられず、異常な脱毛につながるケースがあるのです。
特に一年の中で最も紫外線が強いのは春から夏のシーズン。頭皮や今生えている髪の毛を守るため、日傘や帽子などの紫外線防止グッズを使い予防対策を忘れないようにしましょう。
血行不良
(出典:(7)Ritsuko Ehama 「Infuluence of Scalp Problem on Physical Properties of Hair and Their Prevention by Plant Extracts」)
頭皮の血行不良は抜け毛が増える原因になります。毛髪1本1本に栄養を送り届けているのは、頭皮にたくさん張り巡らされている毛細血管です。
しかし頭皮に血行不良が起こると、血の巡りが悪くなり毛髪が発育するのに十分な栄養を送り届けられません。血行不良は運動不足や乱れた食生活、長時間同じ姿勢でいることなどが原因です。
そのため頭皮が硬いと感じた場合は、マッサージをしてほぐし、頭皮の緊張を解くなど頭皮の血流改善に努めましょう。
睡眠
(出典:(8)睡眠関連ホルモンの計測)
質の高い睡眠は抜け毛予防には重要です。睡眠不足は自律神経やホルモンバランスの乱れに直結します。
睡眠は日中に受けたストレスや外的刺激によるダメージを回復させる大切な時間です。睡眠が十分にとれないと頭皮や髪にダメージを残したまま次の日を迎えてしまいます。
また髪の発毛を促進させる成長ホルモンのほとんどは睡眠中にしか分泌されません。最も分泌が多い時間帯は22時から2時までの間といわれています。つまりこの時間帯に良質な睡眠をとっていることが、抜け毛予防には非常に大切なのです。
抜け毛予防に欠かせない! AGAの早期発見

AGAとは?
(出典:(9)男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン 2017 年版)
AGA(男性型脱毛症)とは男性ホルモンに影響を受け、脱毛する進行性の疾患です。頭頂部や生え際から脱毛していくパターンが多く、早い方では20代から発症します。
通常、人間の発毛サイクルは成長期、休止期、退行期の3段階を2~6年かけて経ていきますが、AGAの場合は成長期が異常に短くなるのが特徴です。
そのためAGAの方では発毛サイクルが100日前後にまで短くなり、髪の毛が十分に発育しきらないまま休止期、退行期に入り脱毛していきます。
AGAは進行性の疾患なので、早めの対策が進行を抑える最大のポイントになります。
あなたの抜け毛はAGA?
現在の症状から簡易的にAGAかどうかを判断できます。次に示す項目に当てはまるかどうかぜひチェックしてみてください。
・抜け毛が以前に比べて増えた
・生え際が後退し、頭頂部が薄くなっている
・髪が細くコシがない
・父や母の親族に薄毛の方がいる
・睡眠不足、運動不足、食生活の乱れ、ストレスを感じている
・同年代より髪が薄いと感じる
・タバコを吸う
・枕元や洗面所などに落ちている抜け毛が増えたように感じる
あなたがもし上記の項目に多く該当するのであれば、AGAの可能性があります。AGAは適切な治療をすれば進行を抑えるられる疾患です。もし心当たりがあれば、すぐに専門クリニックを受診するなどの対策をしましょう。
どれくらい抜け毛で予防が必要?

毛根の色形
抜け毛の毛根の色形はどのようになっていますか?健康な髪の毛根はマッチ棒のようにぷっくりと丸くなっており、白いのが特徴です。
白くベタベタしたものが付着している、毛根から新しい毛が生えている、毛根自体がなく直線状である、ギザギザとした形をしている、いびつな形をしているなどの場合は異常脱毛かもしれません。
頭皮の環境悪化や髪に栄養が十分供給されないまま脱毛している可能性があります。
抜け毛の太さ・長さ
抜け毛予防には、抜け毛の太さや長さを見ることも大切です。抜け毛にハリやコシがあるかどうか確認しましょう。
健康な髪の毛は太さやツヤがありますが、栄養不足の髪は細く軟弱でコシがありません。 これには頭皮の血行不良や硬さに加え、喫煙、日頃の食生活の偏りなどが影響しています。
毛髪の長さが異常に短い場合は、正常な発毛サイクルを終える前に脱毛をしている可能性があります。
抜け毛の本数
人間の頭部には約10万本の髪の毛が生えており、通常1日平均50~100本の髪の毛が脱毛するといわれています。1年の中で最も抜け毛の量が増えるのは秋で、これは冬毛に生え変わる体内サイクルと夏場の紫外線ダメージによるものです。
しかし1日の脱毛量が150本を超えると、異常脱毛の可能性があります。髪の毛が正常な発毛サイクルを終える前に退行期に入り、抜け落ちているということです。
生活習慣の改善で抜け毛予防!

バランスの良い食事
-レバー
(出典:(10)日本食品標準成分表 肉類)
レバーは抜け毛の予防に非常に効果的といわれています。レバーにはビタミンや鉄分、亜鉛などが豊富に含まれており、その中でも亜鉛は髪の毛のキューティクルを作るのに欠かせない栄養素です。
亜鉛は体内で作れず食材から摂る必要があるため、レバーは髪の毛に良い食材といえます。
-フルーツ
(出典:(11)日本食品標準成分表 果実類)
フルーツは健康な髪の毛を発毛させる頭皮環境を整えるのに非常に適した食材です。フルーツには多くのビタミンが含まれており、これらの栄養素は頭皮の血の巡りを改善する、毛髪の細胞の新陳代謝を活発にする、髪の毛に効率よく栄養を送り届ける役割を担っています。
-ナッツ
(出典:(12)日本食品標準成分表 種実類)
ナッツにはタンパク質や亜鉛、ビタミンなどが含まれ髪の毛を作るために必要な材料を多く含む食材です。ナッツに含まれる不飽和脂肪酸は頭皮の血行を促す効果があり、頭皮から髪の毛への栄養補給をスムーズにしてくれる効果があります。
-納豆
(出典:(13)日本食品標準成分表 豆類)
納豆の原料の大豆に含まれる大豆イソフラボンは重要な栄養素です。薄毛には男性ホルモンが影響していますが、大豆イソフラボンを取り入れると男性ホルモンの働きが弱まるため、抜け毛の予防に効果があるといわれています。
-小豆
(出典:(14)日本食品標準成分表 豆類)
小豆はポリフェノールを豊富に含む食材です。ポリフェノールには血液をサラサラにして血の流れを良くする働きがあり、その効果は頭皮も例外ではありません。頭皮の血流は毛髪への栄養をスムーズに送る助けとなり、抜け毛や育毛に良いとされています。
-青魚
(出典:(15)日本食品標準成分表 魚介類)
青魚に含まれるドコサヘキサエン酸(DHA)やエイコサペンタエン酸(EPA)は頭皮の血管を柔らかくしたり、血液の中の脂肪分を除去し血をサラサラにする働きを持っています。そのため食生活が乱れがちな方、油物が大好きな方にはおすすめの食材です。
飲酒と喫煙も抜け毛の大敵!
-飲酒
(出典:(16)e-ヘルスネット 「アルコールの消化管への影響」)
抜け毛を予防したいなら飲酒は適度に抑えましょう。その理由となるのはカロリー過多と栄養素の不足です。
アルコールの取りすぎで体重が増加し、体内に余分な脂肪が蓄積されると、頭皮から皮脂が過剰に分泌され毛根に付着、結果的に発毛の妨げとなります。
また体内でアルコールを分解するには、栄養素が必須です。本来なら髪の発育に使われるはずの栄養分が、アルコールの分解に回され髪の栄養不足を招く結果となるでしょう。
-喫煙
(出典:(17)禁煙科学 vol.9(06),2015.06)
抜け毛の予防には喫煙は厳禁です。タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させ、頭皮を硬くし血の巡りを悪化させます。その結果、髪が細い、コシがない、発毛サイクルが終わらないまま脱毛するなどの症状に直結し、抜け毛を進行させるのです。
加えてタバコを吸うとできる活性酸素は、細胞を傷つけ老化を早めます。それに伴い毛母細胞の分裂が衰え、抜け毛が増える原因となるでしょう。
抜け毛が気になる方は禁煙も検討してください。
十分に睡眠をとる
(出典:(18)睡眠関連ホルモンの計測)
抜け毛を予防するなら、しっかりと質の良い睡眠をとりましょう。睡眠時間がとれていても眠りが浅かったり、不規則な時間に睡眠をとるのでは意味がありません。
特に成長ホルモンが分泌される22~2時までの間は育毛に最適なゴールデンタイムです。
もしも普段の眠りが浅いと感じる方は、照明や騒音などの睡眠環境を整えたり、リラクゼーション効果のある音楽を活用するなど、より質の高い睡眠を得られるようにしましょう。
適度な運動
(出典:(19)顕微鏡血流観察による有酸素運動前後の 毛細血管血流速度の定量)
抜け毛を予防するには適度な運動を生活に取り入れましょう。運動には日頃たまったストレスを発散させる効果があるほか、自律神経のバランスを整え全身の血液の流れを促す効果があります。
ほかにも新陳代謝を促し、新しい毛髪の細胞分裂を活発にする作用がある点も抜け毛予防には良い影響を与えます。
運動は継続的に行っていくことがポイントです。休日や仕事の合間にうまく続けていけるようスケジュールを整えましょう。
正しいヘアケアで抜け毛予防!

シャンプー
(出典:(20)洗浄料とその作用)
-汚れは落とすけど潤いを!
毎日の入浴時、抜け毛予防には適切なシャンプーが必要不可欠です。頭皮の潤いは残しつつ余分な皮脂や汚れだけをしっかりと落としてくれるシャンプーを選びましょう。
シャンプーの洗浄成分は一様ではなく、最も抜け毛予防に適しているものはアミノ酸系のシャンプーです。アミノ酸系シャンプーは、保湿力が高く皮膚と同じ弱酸性であるため、頭皮や髪の毛に負担をかけず汚れだけを洗い落としてくれます。
-頭皮ケアの成分も確認!
(出典:(21)洗浄料とその作用)
抜け毛の予防対策をするなら頭皮(スカルプ)ケアの成分も確認しましょう。
抜け毛を予防したいならシリコンが入っていないノンシリコンシャンプーがおすすめです。シリコンは髪の毛の指通りや洗い上がりを良くする効果がありますが 、毛穴の詰まりや頭皮に膜を作るなど、育毛剤の浸透を妨げる原因となりスカルプケアには適していません。
その他、清涼感を得る目的でエタノールが配合された商品は、頭皮の水分を奪いながら蒸発し乾燥につながるため、抜け毛が気になる方は避けた方が良いでしょう。
洗髪方法
まずは入浴前にブラッシングをしましょう。汚れを浮かせ髪の絡みを解きほぐすことが大切です。
次にぬるま湯で髪についたほこりや汚れを洗い落としてから、シャンプーを手のひらで泡立て髪に塗布しましょう。
指の腹で丁寧に頭皮をマッサージするように洗うか、もしくはシャンプーブラシでもみほぐすように洗髪をすると、頭皮がじんわり暖かくなる感覚があると思います。
すすぎ時は洗い残しがないようしっかりと洗剤を落としてください。最後に必要であればリンスやトリートメントで仕上げます。
育毛剤
(出典:(22)男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン 2017 年版)
抜け毛の予防には日常生活の改善、マッサージやシャンプーと併せて育毛剤も使用すると効果的です。育毛剤には髪の毛を太くする効果、ハリやコシを与えたり、頭皮環境を整える効果があります。
育毛剤を購入する際は、医薬部外品と記載のあるものを購入しましょう。医薬部外品には一定の効果が認められる有効成分が含まれ、頭皮の炎症を抑え、血行を促進するなど育毛に良い環境を整えることにつながります。
サプリメント
(出典:(23)中村博範 「マウスのタンパク質栄養状態と体毛タンパク質合成の 関係について」)
髪の毛を構成しているタンパク質の元となるアミノ酸、髪の毛を作る過程で必須となる亜鉛、その他ビタミンやコラーゲン、植物エキスなど内容は商品によって様々です。
錠剤やカプセルなどのサプリメントで手軽にバランスよく栄養素を補えるのは、忙しい現代人にとってメリットといえるでしょう。
頭皮マッサージ
(出典:(24)Ritsuko Ehama 「Infuluence of Scalp Problem on Physical Properties of Hair and Their Prevention by Plant Extracts」)
頭皮のマッサージには抜け毛を予防するうえで非常にメリットがあります。現代人はパソコンやスマホの使用、ストレスにより血行が悪く頭皮が硬くなりがちです。
マッサージにより頭皮に刺激を与えることは毛根の細胞に刺激を与え、発毛しやすくする効果、血流を促す効果、リラックス効果が期待できます。
指の腹を使って優しくこめかみから頭頂部に向けて押してみてください。続けることで頭皮が柔らかくなり、新しい髪が生える環境が整います。
抜け毛予防のまとめ

この記事では抜け毛の原因と対策、AGA の解説、セルフチェック、髪に良い食材などをご紹介しました。抜け毛の原因はいくつもあり、それらが絡み合い進行していきます。対策もどれか1つをすれば解決するものではないのです。
しかし頭皮のマッサージや、アルコールの摂取量を減らす、早めに就寝するなどの対策は今日からでも行いやすいのではないでしょうか。もしあなたが抜け毛予防をしたいなら、今日からさっそく始めましょう。
文献
1).特集 脱毛性疾患の病態と治療 / 順天堂医学37(4) 1992 年 37巻 4 号 p. 572-586
2).5).植木理恵:都民公開 講座アンチエイジング 順天堂醫事雑誌.2013:59 :P. 327〜330
3).化学と生物/48 巻 (2010) 1 号/2010 年 48 巻 1 号 p. 4-6
4).毛髪の科学と診断 第4版 / 薬事日報社, 2012.11 / P.46
6).J. Son. Cosmet. Chem. Jpn. 特集総説48(4): 2014 / P.271~P.277
7).24). J. Son. Cosmet. Chem. Jpn. 52(1) : 16-23
8).生体医工学 46(2):169-176 解説特集:睡眠の生体計測技術
9).22).日皮会誌:127(13),2763-2777,2017(平成 29) P.2763~2777
10).日本食品標準成分表2020年版(八訂) 肉類
11).日本食品標準成分表2020年版(八訂) 果実類
12).日本食品標準成分表2020年版(八訂) 種実類
13).14).日本食品標準成分表2020年版(八訂) 豆類
15).日本食品標準成分表2020年版(八訂) 魚介類
16).e-ヘルスネット > 飲酒 > アルコールによる健康障害 > アルコールの消化管への影響
17).禁煙科学 9巻(2015)-06 P.1~P.14
18).生体医工学 46(2):169-176 解説特集:睡眠の生体計測技術
19).日温気物医誌第 78 巻 4 号 2015 年 10 月 353
20).21).日本香粧品学会誌 Vol. 42, No. 4, pp. 270–279 (2018)
23).川崎医療福祉学会誌 Vol. 22 No. 2 2013 200 − 207
監修者紹介
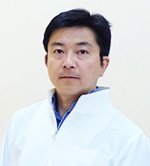
- 稲葉 岳也
- いなばクリニック
■ プロフィール
東京慈恵会医科大学卒業後、千葉大学大学院にて医学博士取得。東京慈恵会医科大学附属病院、聖路加国際病院を経て、2004年にいなばクリニックを開業。皮膚科・形成外科領域のレーザー治療、及びアレルギー疾患の総合的治療が専門です。皮膚科、美容皮膚科、形成外科、美容外科、耳鼻咽喉科、呼吸器内科、アレルギー科を主体として、幅広い視点で総合的な診療を行っております。レーザー機器を導入した医療を行っており、幅広い年齢層を対象としたホームドクターとして、地域密着の診療に尽力しております。