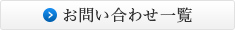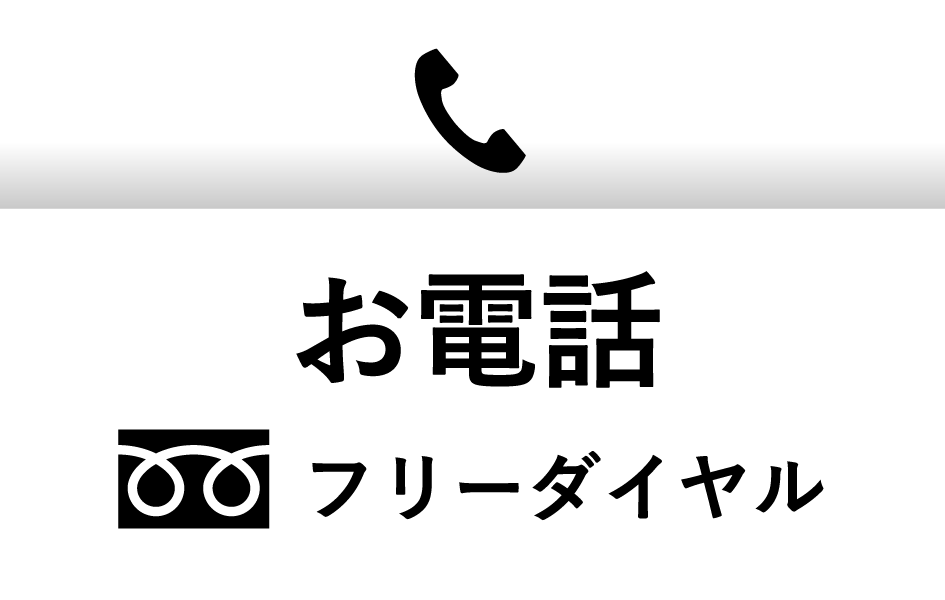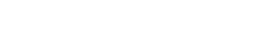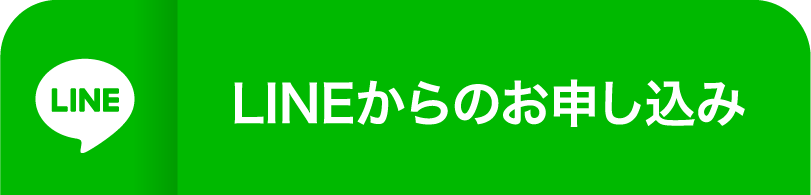監修者紹介

- 佐藤明男
- 東京メモリアルクリニック理事長
さとう美容クリニック院長, 北里大学医学部客員教授, 日本形成外科学会専攻医, 日本臨床毛髪学会理事, 日本先進医師会特定認定再生医療委員会委員長, SKIファーマ株式会社副社長
頭髪に関する内科治療と外科治療まで幅広く実践し、毛髪研究、教育も積極的に行っている。
睡眠不足の解消は、薄毛改善の手段としてよく挙げられる項目のひとつです。
しかし「睡眠不足がなぜ薄毛と関係するの?」と疑問に思う人も多いのではないでしょうか。
睡眠は髪の成長に密接に関わっているため、睡眠習慣の改善は薄毛に対する重要なアプローチだといえます。
この記事では睡眠不足と薄毛の関係について解説します。睡眠習慣を改善するコツも紹介するので、薄毛対策に取り入れてみてください。
目次
睡眠不足が薄毛の原因?

(出典:(1)Lactiplantibacillus plantarum subsp. plantarum N793 株含有ローションの頭皮への塗布による薄毛に悩む男女の毛髪に及ぼす影響)
(出典:(2).百薬の長の効能のメカニズムを探る)
(出典:(3).睡眠からみた小児睡眠呼吸障害)
(出典:(4).循環器疾患と睡眠)
(出典:(5)髪の健康を考える〜美しい髪で過ごすには〜**)
(出典:(6).男性型脱毛症と育毛有効成分)
(出典:(7)社会的ジェットラグがもたらす健康リスク)
睡眠不足は薄毛の原因になることがあります。睡眠不足が体に影響を及ぼし、間接的に髪の成長を妨げるためです。
睡眠不足が薄毛につながる原因のひとつは、成長ホルモンの減少です。成長ホルモンは入眠直後のノンレム睡眠時に多く分泌され、IGF-1の産出を促します。
IGF-1はインスリン様成長因子とも呼ばれ、髪の成長期を支える重要な成分です。欠乏すると髪が細くなったり折れやすくなったりすることがわかっています。
睡眠不足による血行不良も薄毛の遠因です。深い睡眠であるノンレム睡眠時には、末梢血管の血行がよくなります。反対に睡眠習慣が乱れて深い睡眠がとれなくなると、血行の悪化により髪をつくる細胞に栄養を届けられなくなってしまうでしょう。
また睡眠不足はエネルギー代謝の低下も招きます。髪をつくる毛包や毛母細胞は活動の際に多くのエネルギーを必要とするため、睡眠不足によってエネルギーを代謝しにくい状態が続くと、髪の成長にも悪影響が出る可能性が高まるでしょう。
睡眠の仕組み

(出典:(8)重症患者の睡眠管理)
(出典:(9)【魚沼】メンタルヘルスシリーズ第2回 「最近よく眠れていますか?」)
人が眠っているときは浅い睡眠であるレム睡眠と、深い睡眠のノンレム睡眠が交互に訪れます。入眠直後にまずノンレム睡眠が訪れ、その後はレム睡眠・ノンレム睡眠の周期が約90分ごとに繰り返される仕組みです。
レム睡眠時の脳は眠っている状態でありながら、活発に活動している状態です。ノンレム睡眠に比べて交感神経がはたらいているため、まぶたの下で眼球が活発に動いたり、呼吸が不安定になったりします。
レム睡眠中は起きている間に受けた刺激や、学習したことなどの整理が行われています。夢を見るのもレム睡眠の間です。
ノンレム睡眠は脳も休息に入り深くぐっすりと眠っている、いわゆる熟睡の状態です。人の睡眠の約80%を占めているとされています。
ノンレム睡眠では脳の疲労回復や体の成長、傷の治癒などが促されます。免疫力を高めるのもノンレム睡眠の役割です。
良質な睡眠のための睡眠習慣

ここからはおすすめの睡眠習慣を紹介します。良質な睡眠を得るために、以下の睡眠習慣を実践してみましょう。
- 夕食は就寝3時間前までに済ませる
- 就寝前のカフェイン・アルコールの摂取を控える
- 就寝2時間前に入浴する
- 寝室の光環境を整える
- 就寝前にストレッチをする
- 朝にしっかりと日光を浴びる
夕食は就寝3時間前までに済ませる
(出典:(10)大学生における就寝前の夕食習慣と睡眠障害発症の関連)
(出典:(11)睡眠の質を高めよう)
良質な睡眠を得るためには夕食を就寝の3時間ほど前までに済ませましょう。夕食の時間と就寝時間を離すと体のリズムが保たれやすく、質のよい睡眠につながるためです。
夜に睡眠をつかさどるホルモンであるメラトニンが分泌されることで、人は眠りにつきやすくなります。しかし就寝時間近くに夕食を食べると、概日リズムや体内時計などと呼ばれる体のリズムが乱れ、メラトニンの分泌が抑制されます。
メラトニンの分泌が減少すると質のよい睡眠がとれなくなり、睡眠障害を発症することもあるため注意が必要です。就寝時間と夕食の時間が近い人は、食事の時間を調節してみましょう。
就寝前のカフェイン・アルコールの摂取を控える
(出典:(12)【魚沼】メンタルヘルスシリーズ第2回 「最近よく眠れていますか?」)
(出典:(13)健康づくりのための睡眠指針 ~快適な睡眠のための7箇条~)
カフェインやアルコールを控えることも良質な睡眠につながります。
カフェイン飲料には覚醒効果があり寝つきを悪くします。就寝4時間前以降には飲まないようにしましょう。
またお酒を飲むとリラックスして眠くなることから、寝つきをよくするために寝酒をする人は少なくありません。しかし体内でアルコールを分解する際に眠りが浅くなり、睡眠の質が低下してしまいます。
さらに毎日の寝酒を習慣づけることでアルコールへの耐性がつき、徐々に飲酒量が増えていくことも少なくありません。生活習慣病やアルコール依存症につながる恐れがあるため、寝酒は避けましょう。
とくに睡眠導入剤とアルコール飲料の併用は、決してしないようにしてください。薬の作用が強まり、記憶障害やふらつきなどの副作用が出る恐れがあります。
就寝2時間前に入浴する
(出典:(14)シャワー浴からバスタブ浴への行動変容が睡眠と作業効率に及ぼす効果について)
(出典:(15)睡眠の質を高めよう)
就寝の2時間前に入浴することも睡眠の質を高める方法のひとつです。しっかりと体を温めることが快眠につながることがわかっています。
眠りにつく前の体は、末梢血管が広がり皮膚温度が上昇します。熱を放散して深部体温が下がると、眠気を覚える仕組みです。入浴によって深部体温が上がり、その後下がることで、スムーズに入眠できるとされています。
なお入浴のタイミングは就寝2時間前が目安です。入浴で体温が約0.5度上がると入眠しやすくなるため、シャワーだけではなく湯船でしっかりと体を温めましょう。湯温42度で5分程度、湯温38度なら20~30分が目安です。
寝室の光環境を整える
(出典:(16)良質な睡眠のための環境づくり -就寝前のリラクゼーションと光の活用-)
(出典:(17)健康コラム(18-2)睡眠とスマートフォンの関係)
寝室の光環境を整えるのもひとつの方法です。ぐっすりと眠るためには光環境が重要であることがわかっています。
質のよい睡眠に欠かせないメラトニンは、明るい環境にいるほど分泌が抑制されます。メラトニンが抑制されると覚醒度が上がり、スムーズに入眠できません。また睡眠中もまぶたを通して光を感じると、眠りの質に影響を及ぼすことがあります。
メラトニンの分泌を促すためには、暗めで色温度の低い赤みを帯びた光が適しているとされています。就寝前は足元や手元が見える程度に部屋の照明を落として、眠る準備を整えましょう。
またスマートフォンやパソコンが発するブルーライトは強い光線なので、目に入ると交感神経が優位になり目が覚めてしまいます。スマートフォンやパソコンは寝室に持ち込まないことをおすすめします。
就寝前にストレッチをする
(出典:(18)良質な睡眠のための環境づくり -就寝前のリラクゼーションと光の活用-)
就寝前にストレッチをするのもおすすめの方法です。ストレッチをすることで体がよりリラックスした状態になり、入眠がスムーズになります。
ストレッチには下記のような効果があります。
- 関節の可動域を広げ、筋肉の動きを滑らかにする
- 血行を促進する
- 筋肉や神経の緊張を和らげる
気持ちよく眠りにつくためには心身の緊張を解き、副交感神経を優位にする必要があります。筋肉のコリや精神的ストレスが気になる人は、就寝前のリラックスタイムにストレッチを取り入れてみましょう。
朝にしっかりと日光を浴びる
(出典:(19)睡眠の質を高めよう)
(出典:(20)良質な睡眠のための環境づくり -就寝前のリラクゼーションと光の活用-)
朝にしっかりと日光を浴びることも大切です。
人の体内時計は25時間周期なので1日24時間とのズレを修正する必要があります。朝起きたときに日光を浴びることで体内時計がリセットされるので、夜同じ時間に入眠しやすくなります。
また起床直前に徐々に光が強くなる「漸増光」を浴びることもおすすめです。部屋が明るくなると体が起きる準備をはじめるため、睡眠状態から覚醒状態への移行がスムーズになり、すっきりと目覚められることがわかっています。
寝室に遮光カーテンを設置している場合は、少しカーテンを開けておきましょう。徐々に朝日が差し込むことで天然の漸増光として活用できます。
睡眠時に薄毛になりやすい行動

睡眠時に薄毛になりやすい行動2つを紹介します。薄毛対策に取り組むなら睡眠の質を高めるだけでなく、薄毛の原因になる以下の行動をなるべく避けることが大切です。
- 不潔な状態の枕や枕カバーを使用する
- 入浴後に髪を乾かさずに寝る
不潔な状態の枕や枕カバーを使用する
(出典:(21)寝具の真菌実態調査および手入れの効果)
不潔な状態の枕や枕カバーを使用することは避けましょう。不衛生な状態の寝具を使うと頭皮をはじめ、皮膚の健康状態が損なわれる恐れがあります。
寝具は体に密着する時間が長いため、汗やフケなどで汚れやすい環境といえます。
枕やシーツにつく汚れは、真菌が好むエサになります。人の体温や汗による適度な湿気も、真菌にとって快適な環境をつくる一因です。
そのため、枕や枕カバーをお手入れせずに使っていると、真菌がどんどん繁殖してしまうこともあります。
汚染された寝具は皮膚疾患の原因のひとつです。皮膚疾患によって頭皮環境が悪化すれば、髪の生育にも悪影響を及ぼす可能性があります。
枕や枕カバーは定期的に洗浄・天日干しを行い、細菌が繁殖しにくい清潔な状態を保ちましょう。
入浴後髪を乾かさずに寝る
(出典:(22)マラセチア関連疾患)
(出典:(23)生活環境中の真菌とその生態)
入浴後に髪を乾かさずに寝るのもよくありません。頭皮に雑菌が繁殖しやすくなり、頭皮トラブルに発展する恐れがあります。
多くの皮膚トラブルを引き起こす真菌は、湿度が高い場所を好みます。また有機物汚れがある場所や20℃~30℃に保たれている場所も、真菌にとっては居心地のよい環境です。
シャンプーで落とし切れなかった皮脂・フケや乾かしていない髪の水分、人の体温で適度に温められている頭皮は、真菌の繁殖に好都合といえます。
入浴後はドライヤーでしっかりと髪を乾かして、真菌が繁殖しづらい頭皮環境を心がけましょう。
年齢別理想の睡眠時間

(出典:(24)睡眠と認知機能の関係 ~長時間の睡眠や昼寝のし過ぎはNG~)
理想の睡眠時間は年齢によって異なります。個人差や季節による差もありますが、大きくわけると以下のとおりです。
| 若年世代 | 7~8時間 |
|---|---|
| 中年世代 | 6.5時間 |
| 高齢者世代 | 6時間 |
睡眠不足による体への害はよく知られていますが、実は眠りすぎも体によくありません。長く眠りすぎると睡眠の質が下がり、長時間寝たにもかかわらず熟睡感が得られないこともあります。
また9時間以上の睡眠は、アルツハイマー病のリスクを高めることがわかっています。さらに昼寝の時間が長かったり一日に何度も昼寝をしたりすると、睡眠の質が下がり、認知機能が低下するリスクもあるので注意が必要です。
質の高い睡眠を適切な時間とることが何よりも大切です。
睡眠のゴールデンタイム

(出典:(25)本邦の睡眠関連問題とその予防・改善に資する運動の可能性)
成長ホルモンは22時~翌2時に活発に分泌されるため睡眠のゴールデンタイムとする説があります。
しかし近年では時間帯を問わず入眠直後の徐波睡眠に、成長ホルモンの分泌が活発になることがわかっています。そのため睡眠のゴールデンタイムは必ずしも22時~翌2時ではないとする説が有力です。
ただしあまり遅い時間に就寝すると明け方に訪れるレム睡眠と徐波睡眠の時間が重なり、睡眠の質が下がってしまいます。
徐波睡眠がしっかりとれる時間を逆算すると、ゴールデンタイムとされる22時前後の就寝が理想的だといえるでしょう。
まとめ
睡眠不足はさまざまな心身の不調を招き、間接的に薄毛の原因になることがあります。薄毛が気になる人や薄毛を予防したい人は、睡眠習慣の見なおしも取り入れましょう。
また睡眠時間が長ければよいわけでなく、ぐっすりと深く眠ることが大切です。就寝前の習慣や寝室の環境に加え、日中の生活習慣を見なおすことで、睡眠の質を高められるでしょう。
文献
1).日本乳酸菌学会誌 33 (3), 206-214, 2022-11-15
2).日本醸造協会誌/105 巻 (2010) 5 号
3).日本耳鼻咽喉科学会会報/115 巻 (2012) 9 号
4).日本内科学会雑誌 105 (Suppl), 108b-109a, 2016
5).順天堂醫事雑誌/59 巻 (2013) 4 号 p. 327-330
6).油化学/44 巻 (1995) 4 号p. 266-273
7).日本内科学会雑誌/105 巻 (2016) 9 号p. 1675-1681
8).日本集中治療医学会雑誌/24 巻 (2017) 4 号p. 389-397
9).12).新潟県ホームページ
10).栄養学雑誌/81 巻 (2023) 2 号 p. 61-67
11).所沢市
13).広島市公式ホームページ|国際平和文化都市
14).日本温泉気候物理医学会雑誌/78 巻 (2014-2015) 4 号 p. 341-352
15).19).所沢市
16).18).20).バイオメカニズム学会誌/29 巻 (2005) 4 号 p. 194-198
17).京田辺市
21).生活工学研究第7巻第1号(2005-02-10)
22).Medical Mycology Journal/53 巻 (2012) 2 号p. 97-102
23).アレルギー/54 巻 (2005) 6 号 p. 531-535
24).とりネット/鳥取県公式サイト
25).理大 科学フォーラム(2023年 6月)
監修者紹介

- 佐藤明男
- 東京メモリアルクリニック理事長
■ プロフィール
1957年新潟県生まれ。北里大学医学部卒業。
1998年、厚生省(当時) 高度先進医療推進事業でオックスフォード大学医学部客員研究員として英国に国費留学し、帰国後、東京メモリアルクリニック・平山副院長を経て院長に就任。医療法人TMC理事長を兼任。これまで10,000人を超えるAGA(男性型脱毛症)患者を治療してきた実績を持つ、頭髪治療の第一人者。
■論文・出版情報
2007年 『医療的育毛革命』
2009年 『なぜグリーン車にはハゲが多いのか』